この記事は約5分で読めます
最近『健康経営』という言葉をよく耳にするようになりましたね。
社員の健康を守ることが、企業の成長や業績アップにつながる時代です。
特に生活習慣病の予防は、企業の成長や生産性を左右する大きな課題になっています!
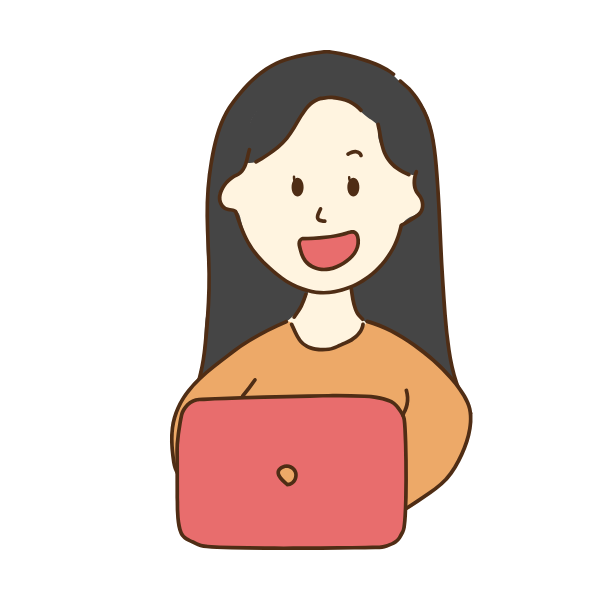
私の会社でも健康経営が話題になっていますが、企業では実際にどんなことをやっているのでしょうか?

健康診断や運動イベント、アプリを使ったセルフチェックなど、企業によってさまざまですよ!
Sailing Dayの羊一です。
今日は、ちょっとやっかいな『生活習慣病』、また、大企業と中小企業それぞれの生活習慣病予防の取り組みについて比較しながら分かりやすく解説します!
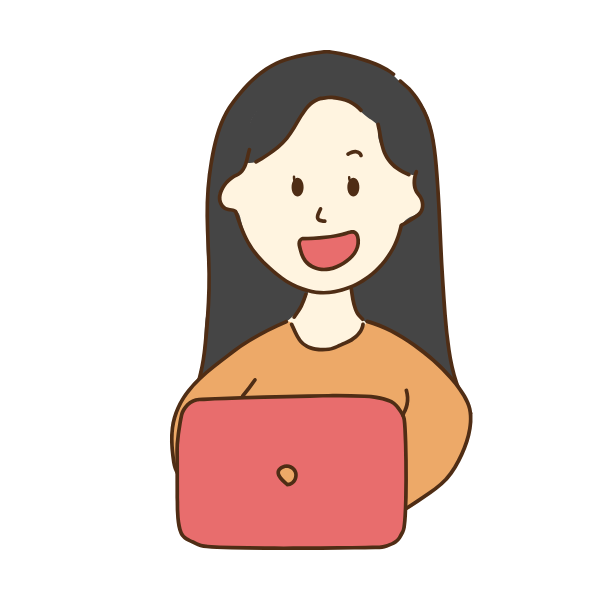
大企業と中小企業ではどんな違いがあるのか気になります!
1.生活習慣病とは?
「生活習慣病」
高血圧症、糖尿病、脂質異常症、肥満症など、食事や運動、睡眠など日常の習慣が大きく関わる病気のこと。

かつては『成人病』と呼ばれていましたが、発症年齢が若年化していることや、生活習慣の改善によって予防・改善できることから『生活習慣病』と呼ばれるようになりました。
生活習慣病の原因や予防法などを見ていきましょう!
(1)生活習慣病の原因
◎食生活の乱れ:高カロリー・高脂肪・高塩分の食事、野菜不足など
◎運動不足:エネルギー消費が少なく肥満をまねく
◎喫煙:動脈硬化やがんのリスクを高める
◎過度の飲酒:肝臓病や高血圧の要因
◎睡眠不足やストレス:自律神経の乱れ、ホルモンバランスの悪化

日常的にやってしまいがちなことばかりなので、『生活習慣病』は厄介ですね!
(2)生活習慣病の予防と改善
◎栄養バランスの取れた食事(減塩・適正カロリー)
◎定期的な運動(ウォーキングや筋トレなど)
◎禁煙・節酒
◎定期健康診断による早期発見・早期対応

定期健康診断のあとに結果があまりよくない人は、「特定保健指導・保健指導」があります!
(3)特定保健指導・保健指導で改善を手助け
日本には、40歳以上を対象に毎年『特定健診(メタボ健診)』が行われ、必要に応じて保健師や栄養士によるアドバイス『特定保健指導』が受けられる仕組みがあります。これは国全体で生活習慣病を減らしていこうという取り組みの一つです。
40歳以上でなくても、健康診断で生活習慣病のリスクが高い人が健診後に受けられる『保健指導』もあります。
『特定保健指導』も『保健指導』も生活習慣病予備軍、もしくはすでに生活習慣病になっているかもしれません…。
企業にとって、社員の健康は大切な資産。
元気に働いてもらうことで、生産性アップや医療費削減、さらには会社のイメージアップにもつながるため、「健康経営」と呼ばれる取り組みが全国で広がっています。

毎日働きに出ている私たちの労働時間は1日の1/3(8時間)ほどですから、企業が健康経営をしてくれていると、それだけで生活習慣が改善されていきます。
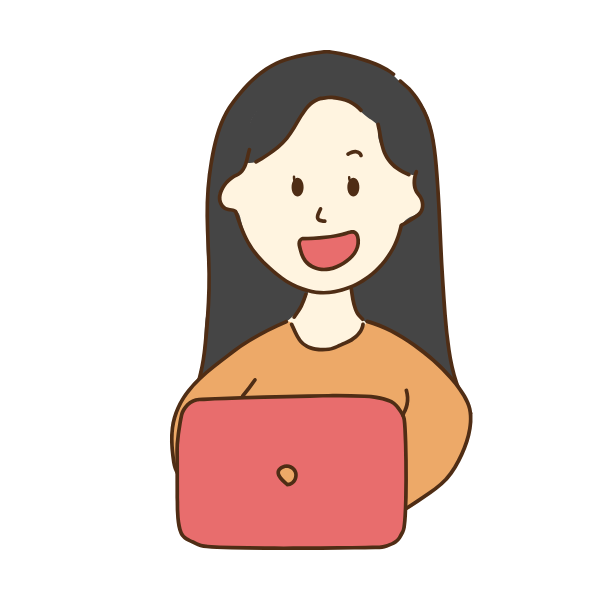
なるほど。それは大きな影響ですね!

実際に企業はどんな取り組みができるのか見ていきましょう。
2.生活習慣病予防の取り組み(5選)
企業でよく行われている生活習慣病対策は、実はシンプルで取り入れやすいものが多いです。ここでは企業が取り組みやすい内容をご紹介します。
(1)定期健診とフォロー
年に1回の健康診断は「体のメンテナンス日」。
血圧や血糖値、体重などをチェックし、病気のサインを早めに見つける。
企業がすべきことは、健診を受けるだけで終わらせないこと。結果を受けて「保健指導」につなげるのが企業の役割。
例えば…
◎健診で「血圧が高め」と出た社員には、産業医や保健師との面談を会社が手配する。
産業医は嘱託契約で月1回など来社することが多く、保健師は健康保険組合や地域の保健センターから派遣されるケースがある(全国健康保険組合 健診後の保健指導・健康相談)。ここで食生活や運動のアドバイスを直接受けられるため、改善へとつなげられる。

「検査して終わり」ではなく会社側が積極的に面談の設定をしましょう!
(2)運動の習慣化
「運動しなきゃ…」と思っても一人ではなかなか続きませんよね。
そこで企業がイベントを仕掛けてくれると、楽しく取り組めるようになります。
例えば…
◎毎朝みんなでラジオ体操
◎部署ごとに歩数を競う「ウォーキングバトル」
◎昼休みに軽いストレッチタイム

こうした取り組みなら、気軽に取り入れられて自然に体を動かす習慣が身につきます。
(3)食生活のサポート
食事は健康の基本。
企業が社員のためにできる施策はいろいろあります。
例えば…
◎社員食堂でヘルシー定食や野菜たっぷりスープを用意。
◎「社内LINEやブログ」で簡単に作れる健康レシピを提供、ランチの選び方も紹介。
◎期間を設定し、食生活改善運動(ポスター掲示で毎日自然に周知できる)をする。
例:腹八分目運動、食べる順番を意識しよう運動など。


腹八分目は午後の集中力にも影響します。
また、コンビニ食でも健康なランチの選び方が分かれば「ちょっと野菜やタンパク質を足してみよう!」と食事習慣を変える大きなきっかけになります。
(4)禁煙・睡眠改善
たばこをやめたいけど一人では難しい…。
そんな社員のために禁煙プログラムを導入する企業もあります。
例えば…
◎成功した人に商品券をプレゼントするなど、モチベーションアップの工夫をしている企業もあり、企業全体で盛り上がります。
また、最近注目されているのが睡眠改善。
例えば…
◎「睡眠セミナー」で眠りの質を上げる方法を学んだり、アプリで睡眠の記録をつけてみたり。
◎ぐっすり眠れるようになると、仕事中の集中力がアップし、生産性もアップするので、企業にとっても社員にとっても良いことしかありません。

『禁煙プログラムと睡眠改善で社員の健康を守り、生産性を上げる!』良いことづくし!
(5)心の健康を守る
体だけでなく、心の健康も大切です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年1回以上ののストレスチェックが義務付けられています。2028年までに50人未満の事業場も「努力義務」から「義務」へと変わります。
◎ストレスチェックで「ストレスが高い」と判定された社員には、産業医や臨床心理士との面談を企業が手配します。これにより、社員は勤務時間内に専門家へ無料で相談でき、早めに不調の芽を見つけて対応できます。
◎**社内相談窓口や外部カウンセリングサービス(EAP)**を設けている会社も増えています。EAPでは電話やオンラインで24時間相談でき、匿名で話せるため「ちょっと疲れてるかも」と感じた段階でも利用しやすいのが特徴です。

実際にストレスチェックを導入した企業では、「相談件数が増えて早期対応が可能になった」「メンタル不調による長期休職者が減った」といった効果が報告されていて、職場全体の安心感や生産性の向上につながっています。

では、実際に企業はどのように取り組んでいるのでしょうか。
ここからは大企業と中小企業の事例を比較して見ていきましょう!
3.大企業と中小企業の取り組みの比較
大企業と中小企業では人手や予算に違いがありますが、どちらも「社員の健康意識を高め行動変容につなげる」点は共通しています。
ここでは 味の素株式会社(大企業) と ナガオ株式会社(中小企業) の事例を見てみましょう。
(1)大企業:味の素株式会社(食品メーカー)
【主な取り組み】
◎AI健康管理アプリ「カラダかわるNavi」
2018年、国内全社員対象に導入。食事や運動をスマホに記録するとAIがカロリー計算・栄養評価を行い、改善提案まで自動表示。社員食堂の食事データもアプリに自動連携し、手入力なしで記録できる仕組みを構築。
◎睡眠改善プログラム
自社製品「グリナ®」を活用し、睡眠の質を高めるプログラムを実施。社員に睡眠の重要性を啓発。
◎先端検査AminoIndex(AIRS®)
血液中アミノ酸バランスから糖尿病発症リスクやがんの可能性を評価する検査を導入。将来の疾病リスクを早期把握。
◎全員面談制度
健康診断後、全社員が産業医・保健師と一対一面談。小さな不調も早期発見・対応可能。
【成果】
◎AIアプリとデータ連携による生活習慣の可視化で社員のセルフケア意識が向上。
◎睡眠改善プログラムにより集中力・業務効率アップを実現。
◎経済産業省・東京証券取引所の「健康経営銘柄」に2017年・2018年連続選定。
(参考:味の素(株)、当社グループの事業を通じて「健康経営」の取り組みを強化より)
(参考:企業向け健康アドバイスアプリ 「カラダかわるNavi」より)

つまり、味の素株式会社はAI健康アプリや睡眠改善プログラム、先端検査、健診後の全員面談などを組み合わせ、社員の生活習慣をデータで見える化して早期対応を徹底することで、セルフケア意識の向上と業務効率アップを実現し、健康経営銘柄にも選ばれた先進企業です。
(2)中小企業:ナガオ株式会社(化学メーカー・従業員61名)
【主な取り組み】
◎セルフチェックシステム
2018年導入。オンライン問診と血圧・体重などを入力するとAIが10分で健康リスクと個別アドバイスを提示。社員が自分ごととして健康に向き合うきっかけに。
◎運動イベントの活性化
社員有志で「ナガオランナーズ(マラソン同好会)」を結成。会社が大会参加費やユニフォーム費用を全額負担。26名が所属し、部署を超えた交流を促進。
地域大会に出場するソフトボール部も活動。2年に1度は社員家族も参加する大会を開催。
◎家族も巻き込む健康づくり
家族参加型の運動イベントや食生活改善の声がけなど、小規模ならではのアットホームな仕組みを整備。
【成果】
◎セルフチェック利用率が社員の9割超に拡大。健康リテラシーが向上。
◎運動・交流イベントを通じた社内一体感の向上。
◎柔軟な働き方の工夫とあわせ、**離職率0.5%(10年間)**という低水準を維持。
◎求職者からも「ワークライフバランスが良い」と高評価を獲得。
(参考:健康経営優良法人 取り組み事例集令和2年3月より)

つまり、ナガオ株式会社はオンライン健康チェックや会社負担のマラソン同好会・家族参加型イベントを通じて、社員と家族が楽しく健康づくりに参加できる環境を整え、社員の健康意識を高めながら離職率0.5%という働きやすさを実現している中小企業です。
| 項目 | 味の素(大企業) | ナガオ(中小企業) |
|---|---|---|
| デジタル活用 | AI健康アプリ+先端検査でデータに基づく包括的対策 | オンラインセルフチェックで簡単に健康リスク可視化 |
| 食生活支援 | 社員食堂とアプリ連携、睡眠改善食品活用 | システム上で個別アドバイス提示(社員食堂なし) |
| 運動促進 | アプリで記録・ランキング機能 | マラソン同好会・家族参加型ソフトボール大会 |
| 社内体制 | 健康管理専門部署、全員面談、復職支援プログラム | 社長主導の施策で社員自主参加を促進 |
| 成果 | 健康経営銘柄連続選定・生産性向上 | 利用率9割・離職率0.5%・採用評価向上 |

味の素株式会社は、自社製品やAI技術を活かしたデータ重視の戦略タイプ。
ナガオ株式会社は、家族参加やイベント型で小規模でも続けやすい仕組みを実現。
アプローチは異なりますが、どちらも『社員が主体的に健康づくりに参加できる環境づくり』が成功の秘訣になっています。
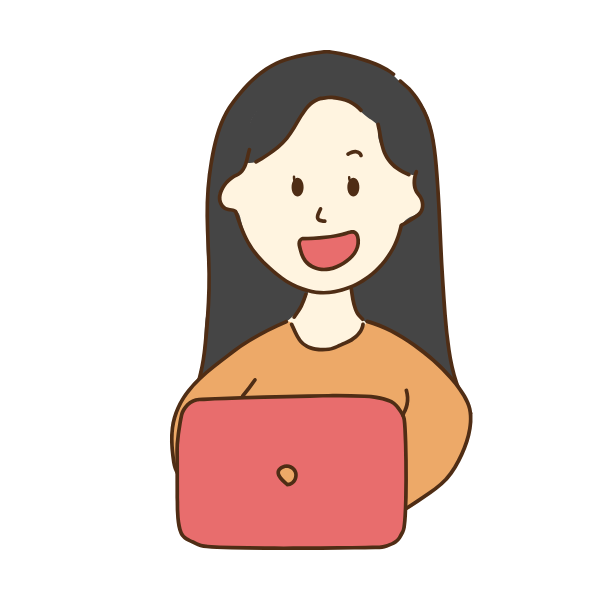
企業が社員の健康への仕組みをつくってくれたら日常的に頑張れて、習慣化でますね!

企業が社員の健康を守るためには、『仕組みを作り習慣化が鍵』ですね!
ぜひみなさんも健康の習慣化を目指しましょう!
4.まとめ
◎健康経営は社員の健康維持が企業成長につながる取り組み。
◎生活習慣病対策は
▶︎健診+面談・運動イベント・食事サポート・禁煙/睡眠改善・メンタルケアが基本。
◎味の素(大企業):AIアプリや睡眠改善、全員面談でデータを活かし社員のセルフケアを強化。
◎ナガオ(中小企業):オンライン健康チェックや家族参加型イベントで楽しく継続、離職率0.5%を達成。
◎規模は違っても、社員が自ら健康づくりに参加できる環境づくりが成功の鍵。

この記事の監修 長谷 有希央
◎安眠インストラクター
◎睡眠&寝具インストラクター
◎健康経営アドバイザー
◎中小企業診断士 の資格を持つ「眠りと健康経営の専門家」です。

